
2025年の中学入試もひと段落し、各塾では入試報告会が開催されていますね。
去年は大手4塾聞きに行った私ですが(暇なのか?)、今年はSAPIXと早稲田アカデミーの報告会に参加してきました。
まずは息子もお世話になっているサピックスから、簡単にまとめたいと思います。
なお、かなりメモが殴り書きだったため、自分でも読めないところがちらほら。
文言が違うところも多々あるかと思いますがご了承ください。
会場は文京区の文京シビックホールでした。
去年も伺いましたが、大江戸線春日駅から直結でアクセス◎です。
今年度の中学入試の傾向
●2月1日午前の受験率は、過去最高の水準だった昨年とほとんど変わらず、15%台を維持した。
この受験率は、2月1日午前受験者数を、首都圏1都3県の公立小学校6年在籍者数で割って求めたもの。
少なくともあと3年間は、首都圏の中学入試の厳しさは変わらないと思われる。
●埼玉県では開智・開智所沢の出願者が大幅に増加し、栄東ののべ出願者数を上回った。
しかし実際の受験者数は栄東が上回った。
また昨年新設された淑徳与野の医進コース、普通コースともに出願者数が大幅に増加した。
●千葉の市川中、東京都立の中高一貫校では男女別の募集定員が撤廃された。
●多くの都立中高一貫校は軒並み出願者数を減らした。
東京都による高校授業料の支援が少なからず影響している可能性がある。
●慶應義塾普通部が人気で出願者数を100名以上増やした。
●豊島岡女子学園が、算数・英語資格入試を新設した。
算数が得意で英語の資格を持つ受験生にとっては、4科目と算数・英語資格入試の2回の判定のチャンスがある入試になった。
●2月2日が日曜日に当たったため、青山学院中等部が入試日を例年の2日から3日に移動させた。
そのため、大学附属校を中心に、2日入試校の出願者数増加と、3日入試校の出願者減少が見られた。
青山学院中等部は男子の出願者数が特に増加した。
●2月の東京入試の倍率が上昇し激戦となっている。
2月に安全校を組み込むのもなかなか厳しいので、1月にお試し受験ではなく、進学先となりうる学校の合格をとっておく傾向にある。
校名を変更して共学化に踏み切ったり大学の系属校になるケースが目立つ
2026年から校名を明治大学世田谷と変更して名台の系属校となり共学化が決まっている日本学園。
この協定が締結された2022年から人気が急上昇している。
練馬区の東京女子学院も2025年より校名を英明フロンティアに変更し高校共学化、2026年から中学も共学化。
鎌倉女子大学中等部・高等部は2026年より校名を鎌倉国際文理と変更して共学化。
2024年に共学化して校名を羽田国際にした大田区の蒲田女子は2026年に中学を開校予定。
東村山市の明法中学・高等学校もすでに共学化している高校に続いて、2025年からは中学も共学化。
中野区の宝仙学園理数インターは2024年に順天堂大学の系属校となり、順天堂大学医学部への推薦枠が設けられた。
入試の日程変更や1科入試も増えている
東京農大第一は2月1日午前入試に新規参入し、中学の募集が175名から200名に増えた。
午後入試では受験生の負担を減らすことのできる1科目入試も、男子校だけではなく女子校でも増えている。
保護者のサポートのコツ
中学入試は子供にとっての自己実現の場。
子供は選手、教師はコーチ、保護者はマネージャー。
名マネージャーになるためには
①プラスのイメージを含む言葉を意識して使う。
例えば、欠点→課題など。
②共感力を高める。子供の今を知り、認めてあげること。
③視野を広げること。人生でいつ何が役に立つかはわからないもの。
各担当教科より
●算数
いわゆる典型題が出題の大半を占めた。
ただし典型題とはいえ、一度見たことがある、あるいは一度解いたことがあるだけで容易に特典ができる問題ばかりというわけではない。
また年々、問題文が長くなる傾向あり。
例えば筑駒を例に挙げると、問題文の文字数が1995年は1500字、2020年は2000字、2025
年は3300字にもなった。
また今年の2025年にちなんだ問題も多かった。
2025は45の平方数、九九表の総和であることを踏まえておく必要があった。
●国語
例年と同様、出版時期が新しい本からの出題が目立った。
直近一年の出版物が全体の37%、直近二年まで広げると52%を占めている。
内容は、受験生が経験したことのないような大人の世界が描かれていたり、古い時代が舞台となる小説であったり、ファンタジー要素を含むものもあり。
普段からどんな文章でも貪欲に読みこなしていく姿勢を保つのが大事。
印象的だったのは、男子校である早稲田中で出題された【見つけたいのは、光】。
キラキラ子育てブログを書いているシングルマザー、そのブログの読者である女性2人(1人は子供がいなくて、1人は子育て中)、その3人が飲み屋のカウンターで論争をするという内容。
これを男子校で出すっていうのがすごい。
この本、気になります。笑
●理科
首都圏主要校における分野別出題率は、生物が増加し、物理・科学・地学が減少した。
4分野からほぼ均等に出題される傾向は大きくは変わりなし。
目の前にある問題にコツコツと取り組み、苦手でも逃げないことが大事。
身近に潜むマニアックなことに興味を持ち、考えたり調べてみたりすること。
家でできる実験(食塩の結晶作りや果汁など)、博物館や自然体験、料理などのお手伝いもおすすめ。
そんな時間、6年生にはあるのだろうか😅
●社会
どの学校を受験するにしても、語句を漢字で正しく書くことはもちろん、歴史の年代、公民で扱う議員定数や任期などの数字を確実に身につける作業から逃げることはできない。
また多くの学校で、粘り強く読み取る必要のある資料読解問題が出題されている。
例え初めてみる資料であっても、よくみて何か自分が知っていることがないか考える姿勢が大事。
時事問題では、新しくなった切手の値段、新紙幣に関するもの、パリオリンピックについて、大阪万博について、キャッシュレス化、現金のメリット、働き方改革、災害、夫婦別姓についてなど。
常に身の回りのことや日々目にするニュースにも注意を払う。
【自分だったらこう考える】と、自分の意見もまとめてみるとなおいい。
まとめ
全体的に、去年の報告会の内容と似ている部分がとても多かったです。
どの教科の先生もおっしゃっていたのが、問題の長文化・・・。
そして一番印象に残ったのは、『中学入試の出題範囲の拡大は限界に近づいている』ということ。
年々内容が難化していて、そろそろ限界だそうです。
地域や学校による出題内容の差がなくなりつつあるそう。
もちろん、問題の量やひねり具合に差はあると思いますが・・・
なんだかすごい時代に子供に中学受験をさせてしまうのだなぁと思いました。
さて、もう息子の受験まで10ヶ月ちょっとです。
早く終わって欲しいような、欲しくないような、複雑な親心・・・。
まとまりのない文章になりましたが、少しでも参考になれば幸いです。
早稲田アカデミーの報告会の様子もまとめられるよう頑張ります!
去年の報告会の様子も貼っておきますのでご参考までに。





![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cfacbc1.89357ac8.1cfacbc2.36145980/?me_id=1213310&item_id=21511687&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4516%2F9784344434516_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


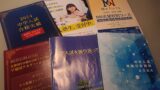




コメント