
先日のSAPIXの入試報告会に続き、早稲田アカデミーの報告会にも足を運んでみました。
会場は、神保町にある日本教育会館。
帰り道お腹が空き過ぎて、カレー屋さんに引き込まれそうになったのはいうまでもありません・・・。
動画視聴
去年と同様、動画放映から始まりました。
早稲アカ名物のハチマキがとにかく印象的でした。
初めはちょっと抵抗あるかもですが、確かに気合いは入りそうですよね。
合宿の様子も放映されていたんですが、勉強だけでなく、山をみんなで散歩したりキャンプファイヤーしたり、楽しみもたくさん盛り込まれていてなんだか安心しました☺️
2025年度中学入試を振り返って
教育本部長の方よりお話がありました。
淡々と話されていてとても穏やかで優しそうな男性でしたが、僕も授業中は人が変わりますよとおっしゃっていて、どのくらい変わるのだろうと気になってしまいました。笑
首都圏に住む小学六年生はおよそ29万人弱。
そのうちの約15%に当たる42800人の児童が、2月1日に受験をした。
2月1日には受験しない受験生も合わせると、受験率は20%程度になるのではないだろうか。
来年以降児童数は少しづつ増えていき、5年後くらいから減る見込み。
予想では、2028年度入試が激戦のピークになりそう。(新小4が受験する年)
受験生の出願校数の平均は8.15校、受験校数の平均は6.32校で、どちらも増加している。
これは多くの学校でネット出願ができるようになってきていることが影響しているだろう。
では一体どうやって受験校をそんなにたくさん決めたら良いのだろうか。
受験プランの立て方の一例をあげてみる。(本命が東京の学校のケース)
まず、2月1日、2日、3日に志望校を組み合わせながらプランを立てる。
1月に持ち偏差値より5〜10低い学校を、一校か二校受ける。
2月1日と2日の午後にも出願する。(偏差値メリハリつけながら)
こうすると、6〜7校受験することになる。
受験者が増えている学校の特徴。
①進学実績、学校の設備が良い
②学校改革をしている、共学化や国際化
③高大連携、付属化、系属化
(↑去年の報告会でも全く同じ文言がありました・・・)
首都圏での受験生はおよそ6万人。
その中で偏差値50以上の子はおよそ3万人。
これは、首都圏の小6のおよそ10分の1に当たる。
偏差値50しかないと思わず、自分は上位10%にいるんだと自信を持って欲しい。
近年高大連携や大学の付属化、系属化が増えているのも、中学の時点から優秀な生徒を確保したいという大学の思いから。
18歳の人口は年々減っていて、大学は優秀な生徒の確保が難しいらしい。
合格実績

これはお話しされていたわけではなく、合格実績の資料を見て私が感じたことです。
普通にすごいですよね、かなり伸びてます。
御三家も早慶もだいぶ増えていて、早稲アカ史上最高数を更新だそうです。
でもこれを見て感じるのは、サピックスも早稲アカも、やはり難関校ばかりクローズアップするんですよね。
もちろんそれが塾としての売りになるわけですから、気持ちはわかるんですが。
娘の時の日能研の合格実績は、難関校順ではなく、五十音順い書かれていたのをふと思い出しました。
各教科担当者より
●国語
近年の中学入試における国語は大学入試改革の影響を受け、決して見過ごすことのできない変化が生じている。
これまでの文章読解と語句や漢字に加えて、時代の流れに沿った新たな出題も積極的に取り入れられている。
『直近二年以内の発表・発刊された作品からの出題』は今年も多くの学校で見られた。
読んだことのない文章をぶつけることで受験生の真の力を試したいという学校側の意図が見て取れる。
特徴的な出題である、複数の文章を用いた出題や表や図を用いた問題などは定番の出題形式として定着した。
難関校では100字を超える長い記述問題も多い。
設問内容を正確に捉え、解答に必要な複数の要素を本文から引き出し、手際よくまとめるトレーニングを重ねるしかない。
また近年見逃すことができないのが、記号選択問題の難化。
一つ一つの選択肢が長くなるとともに細かな表現のニュアンスまで吟味させるものが増えている。
選択肢だけを見てなんとなく選ぶのではなく、本文と丁寧に照らし合わせながら根拠を持って選ぶという論理的な解答姿勢を身につける必要がある。
●算数
中学入試の算数は、学校によって難度、分量、出題分野、形式は様々ではあるがその中でも共通して言えることは、算数が合否に最も影響を与える科目であるということ。
・今年の入試算数の難度は標準であった
・『数』のテーマでの出題が多かった
・典型題プラスアルファでの出題が多かった
・論理的思考力➕知識と技術の習得が試された
・テーマの拡大は緩やかだが、解答形式は多様化している
女子校や共学校での算数1教科入試も増えていて、グラフを用いた出題がかなり増えている。
また女子校でも立体切断の出題が増えている。
今年は2025年ということもあってか数のテーマの出題が多かった。
来年以降だと、2027年と2029年は素数なのでそれにまつわる出題が多そう。
2027年は、10年ぶりの素数。
●社会
アフターコロナを反映してか、ここ数年目立っていた感染症の歴史などに関する出題は減り、日本を訪れる外国人観光客の増加を背景にインバウンドやオーバーツーリズムなどを題材とした出題が目立つようになってきた。
戦後80年に関連し、第二次世界大戦など戦争や軍隊に関する出題も多かった。
また2024年は世界の多くの国で首脳を選ぶ選挙が行われた選挙イヤーだったためか、多くの学校で政治や経済に関する出題があった。
またここ数年の社会」の傾向として、表やグラフをふんだんに用いて、思考力を試す出題が増えている。
このような問題の場合、解答用紙は割とスッキリしていて、受験生は一瞬簡単なのかなと思いがちだが、実際は表やグラフの意味を理解するのに時間がかかるケースが多い。
また、ジェンダー、多様性、旅行、オリンピックなどのテーマも多く上がっていた。
大河ドラマの影響もあってか、紫式部や源氏物語、中宮彰子に関する出題も多かった。
来年は田沼意次の政策に関する出題が増えるかも?!
(息子と毎週べらぼう見てます!!)
来年に向けては、戦後80年、昭和100年ということもあり、引き続き戦争関連の出題が多そう。
また今年開催される大阪万博について、来年のミラノ・コルティナダンぺっツォでの冬季オリンピックについてなども要注目です。
●理科
今年目立った時事問題は、猛暑について。
猛暑日や暑さ指数、熱中症警戒アラートなど。
関東大震災から100年、阪神淡路大震災から30年ということもあり震災についての出題も多かった。
今後起こる恐れもある南海トラフ地震についても出題があった。
日頃からニュースや新聞に興味を持つことが大事だが、もし知らない内容の時事問題が出題された場合でも、設問をよく読み、自分の知っていることと結びつけて考えることが大事。
来年度に向けた時事問題のキーワードは、地震、災害、皆既月食、奄美大島のマングースについて、ノーベル賞や新技術、山火事、など。
早稲アカでは六年の冬季講習で時事問題の対策をするのでご安心をとのこと。
まとめ
去年に比べて、先生方の話し方は熱く、声量も大きく、とても熱い報告会でした。
とても話に引き込まれ、保護者の拍手もサピックスより大きかったです。
去年はもっと淡々としていた印象だったので、去年との違いに驚きました。
去年のものもご参考までに。
サピックスよりも具体的な数字を多く交えながら、わかりやすい報告会だったかなと思います☺️






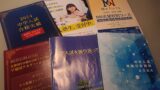


コメント